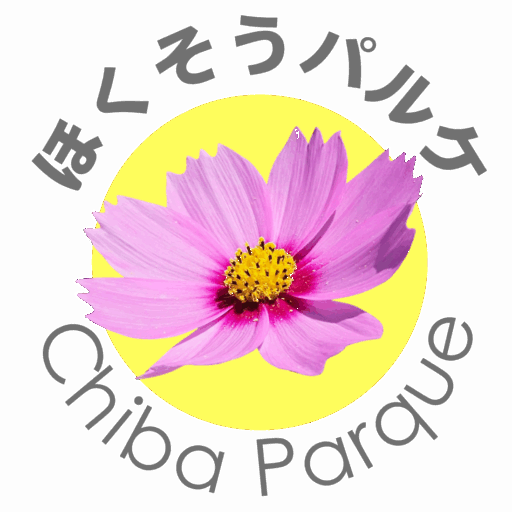あなたもできる防災訓練や救急救命訓練|町内や団体、サークル、学校でできること
もくじ
防災・救命で大切なこと
みなさんこんにちは。
ずっとずっと前に印西市内で防災についてのセミナーに招待させていただきました。
その発信について、どう発信したら見てくれるのか、興味を持ってくれるのかがわからず、なんとなくX Twitter で写真を添えながら「こんなのに行きました。」くらいにしかやっていませんでした。
ただ、最近私自身を含め身の回りで入院や病気などの話が増えたので(ただの歳か)、セミナーの紹介とともに、「ふとしたときに考える」というきっかけづくりの一つとして記事を書きます。
後半はまるごと私の持論や経験に基づくブログです。
今回紹介させていただく団体、町内会とは一切関係のない話ですので流してください。
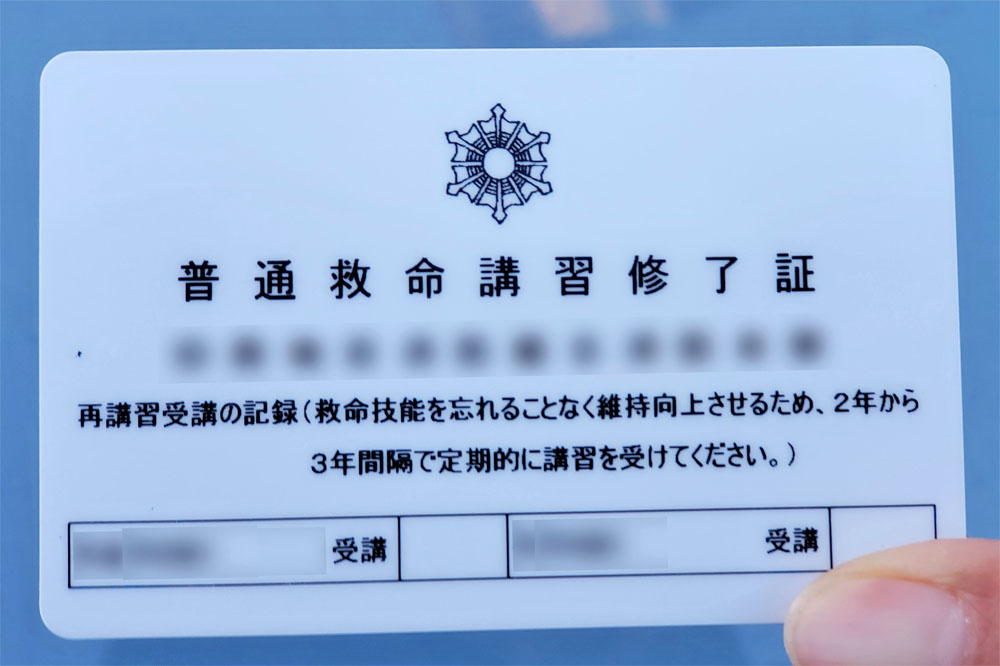
「何を偉そうに。」と言われそうなので・・
まず、私自身がどのような立場から伝えているのかを示さないと説得力も無いので、経験とともに軽く自己紹介します。
過去のへっぽこ経験や性格は後半で説明しています。
1.胸骨圧迫訓練…何度も
2.AED訓練…何度か
3.水難救助訓練…何度か
4.AED対応連携…実践の流れを経験
5.トリアージ訓練…多少
6.消火器訓練…何度か&自宅にある
7.東日本大震災、千葉東方沖地震経験あり
8.手賀沼水害・利根川水害危機についての歴史…旧いんざいパルケに記事アリ
9.ろうあ者の対応…何度か
10.救急車を呼ぶ…実践何度か
11.テロ警戒…実践何度か
12.緊急避難…実践何度か
という感じです。
胸骨圧迫は
いわゆる心臓マッサージといわれてるやつです。乳児も同じく。
水難救助は
うーん、一応海かな(笑)。
どういう一連の流れで、浮き輪をどこに投げるとか離岸流とかそういうやつです。
AEDは
実際仕事中に起きました。
無線連絡で一連の流れを把握、その時は担当の近くだったためリアルにその状況を経験。
トリアージは
助かる見込みがない人はブラックカードで、優先順位は最下位
(きつく言うと助からないから救護しない)というような、
命が助かるか、今すぐ救急車か、様子を見られるか、などの見分け訓練です。
このような状況に実際になったときは胸骨圧迫を行うか、行わないかの判断は私にはできないので、あくまで救助隊がくるまでのお手伝いにしかなりません。
あとは子育て世代だと、チアノーゼって聞いたことがあると思います。
血色や水分、意識の状態など、「いつもと違う」がわからない、など、パニックになってしまいますよね。
ろうあ者
耳が聞こえなかったり、目が見えない人も同じような状況になった場合、どんなにメガホンや放送で流しても聞こえないし、状況はわかりません。
その立場になって、歩いたり、階段を上ったりという経験で、どう対応するべきかの訓練です。
訓練を学んだ場所・団体
これらをどこでやってきたかというと、
・元職場…50%
・印西市の地元の自治会…10%
・学生時代のボランティア経験…10%
・アメリカ暮らし…30%
の4つとなります。
・アメリカ暮らしは、ほぼ実践(見ず知らずの人たちに教えてもらったり見たり)なので、ここでは省きます。
それなりにいろんな場所や所属を経験しましたが、以上の経験を与えてくれたのはたった3か所だけなのです。
逆に言えば、やってるところはすごくやってる、ということにもなり、「自分から考える」きっかけにもなります。
この中で一番大切なことは、
「ふとしたときに自分で考える。意識する。」
ことじゃないかと私は思っています。
持論の前置きはここまでにして、今回は私の話とは全く別の2つの体験をご紹介します。
各自治体にある防災意識の高い団体や組織
各自治体には防災に対して認知を広めようとしてくれている団体や組織がありますので一例をご紹介します。
1. 自主的に立ち上がった防災団体
2. とある地域の自治会

印西市でみんなの防災プロジェクトの講習会に参加させてもらいました。
こういった防災について知識やきっかけを広めてくれる団体がみなさんの地元にもあるかと思います。
みんなの防災プロジェクトとは

「みんなが助かる みんなで助ける」をモットーに、千葉県印西市を拠点にしながら、地域の住民が主体となって進める市民防災活動団体です。
地震災害や水害など自然災害を想定し、
「災害は“非日常”ではなく日常の延長線上にある」と考え、楽しみながら防災を学び、日頃から備える意識を育てることをコンセプトとしています。
子どもから大人まで楽しく参加できる防災イベントや、地域交流を図りながら防災ゲームや体験で防災力を高めていきます。
各地イベントにも出ています
防災という堅苦しそうなキーワードを持ちながらも、楽しく学び意識するきっかけとして、
市内外の楽しいイベント(例えばなんとか祭りなど)にも顔を出したり、出張したりして、より多くの人たちに向けて情報共有を続けてくださっています。
詳しくは下記Instagramをご覧ください。
もしもを意識すること
関東に住んでいるとよく気づくのですが、
例えば地震。
千葉県北西部は地震に強い土地が多いとメディアでもてはやされています。
しかし、実際に都心直下が起きたとして、はたして地元の生活は今日も明日も平和に過ごせるでしょうか?
千葉県は橋がないとほかの都県に行けないのです。(フェリーと飛行機はあるけど)
例えば水害。
都内では水害危険地域として江戸川区がよく話題にあがっていますが、それだけに地下河川や暗渠の整備が整っていて住民の意識も高いです。
実際にちょくちょく冠水が起こるのは杉並区や世田谷区などです。
新しい地域は台地の開発により、自然の防御(森林や土が水を吸ってくれないうえに、川や水路のキャパが無い)などの理由で、水が流れずたまるのが早いのです。これがいわゆる内水被害です。
例えば富士山の噴火。
火山灰の影響は現代は未知数です。
どのくらいの影響で、どのくらい経済や物流がストップするでしょうか。
例えば国際情勢。
いつ何がどう起きてもおかしくないといわれて何十年。
物理的な危機、食料的な危機、インターネットのセキュリティは大丈夫でしょうか。
そんな「もしも」を考えるきっかけを教えてくれる団体です。
私が学んだこと

私がここで学んだことは、
ご近所さんを想像し、いつ、どんなとき、どのご近所さんに何が必要か「考えること」。
年をとって歩くのが困難な人?
というのは想像しやすいですが、その人にはお子さん夫婦が同居していて大丈夫かも。
いや、夫婦は働いているかも。
一見なんでもない若者?
だけど、1人暮らし。
近所づきあいなんて全然ないし、あまり見かけない人。
そんな「ご近所さん」を身近にあてはめて、いざというときにどう行動できるかを考えてみます。
まずは「意識すること、考えること、正しく知ること」からなんですね。

とある町内会の防災訓練に参加させていただきました。
地震を想定し、火災が発生と想定。
消火器の使い方
心肺停止状態の人の救護活動
AEDの使用方法
救急を実際に呼ぶ電話訓練
などを住民のみなさんで体験しました。
参加者には備蓄された水や保存食を配ったり、実際に炊き出しした物を試食してみたり。

私が学んだこと

消防車が来て、消防士さんがレクチャー。
実際にシミュレーションした姿も勉強ですが、
同じように地域の人がやってみたりするとどこでつまずきやすいか、疑問や難しいところが見えてきてわかりやすいです。
これらは抜き打ちなので、前に出てやってる人は相当な緊張ですが、
実際はもっと緊張する場面ですよね。
そういった意味で訓練というのは大切だと感じました。
自治会という組織?の人たちが集まるきっかけのひとつとして重要かつ有意義。
なんだかんだとみなさん楽しそうでした。
救急対応の講習は近くで無料で受けられます
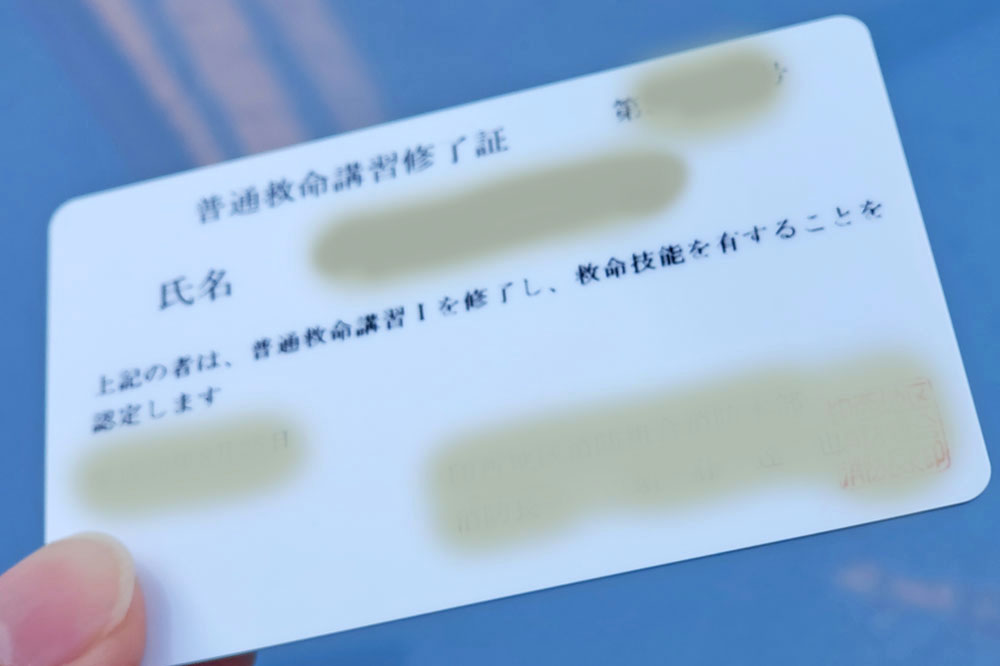
緊急時の対応や救急救命でできることって、私たちには限られた範囲ですよね。
でも、
実はそのひとつだけでもやってくれるだけで、救える命がたくさんあります。
そしてその訓練は、意外と近場で無料でできるのです。
町内会やマンションなどの自治会
所属の趣味の団体
会社
などで
ぜひ2年に1度でもいいからプログラムにいれてみてはいかがでしょうか。
ざっくり紹介すると
地元の消防署にお願いするとたいてい講習をやってくれます。
ちょっと知るだけで何倍も力になる
100%全部知識と訓練をマスターすることなんて無理なことです。
それができたらあなたはすでに職業が違うはず。
けれど、その道のプロが来るまでに、
「状況」「年齢」「呼吸や意識」などを報告して、空振りでもいいから緊急対応ができれば、助かる命が多数にあるんです。
ということを救命にあたる方はほぼ全員おっしゃっていました。
もちろん、自分の命を一番に。
※下記はざっくりです
1. まず深呼吸
吸って吐いてを1:1の速さにすると余計緊張するので、吸って4秒吐いてを8秒など、息を吐く方を吸う速さの倍以上にしましょう。
2. 意識の確認(呼んで肩をたたくなど)
3. 「119」救急車をためらっている場合は「#7001」
4. 住所、年齢、性別、意識の有無、状態など聞かれます。
なるべくスピーカーにするとよいかも。
5. 待ちます。
途中からまた電話くることあります。
指示してくれることもあります。
できる限り応急処置または様子見。
6. 救急車到着
ここから、意識や状況によりすぐ応急対応してくれます。
受け入れ先病院を探すのに30分程 + 受け入れ先病院まで30分かかる場合があります。
この時は緊急ではないと判断されたのだと認識しています。
怒らないようにしましょう。救急隊は最善の手段を選択してくれています。
ドクターヘリ対応の場合、わりとヤバイ状況なので、後悔のないよう可能な限りのことを尽くしましょう。
7. 同行するか、あとで病院に向かいます。子どもの場合は付き添います。
過去に防災用品について書いた記事があります。
よろしければ参考にどうぞ。内容は薄いです。
しかも更新してないです。

我孫子市・印西市・栄町限定となってしまいますが、過去に水害についての記事を書いていますので、ご興味のある方は下記リンク先をご覧ください。
内容は
高台でも水害が多い理由
利根川の堤防の危険水位
利根川手賀沼周辺の水害対策防災池を知ろう
千葉県内の利根川の増水の特徴や避難場所
となります。
更新してないです。

印西市内限定ですが過去にAEDについて書いた記事があります。
よろしければ参考にどうぞ。内容は薄いです。
しかも更新してないです。
現在は印西市がAEDの設置場所を公表していたような・・。
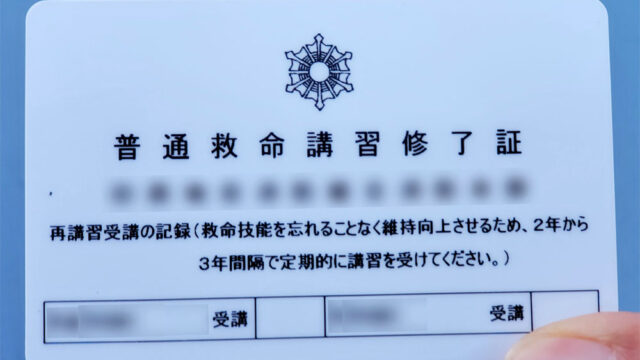
キーワードは
「助け合い」と「日頃から考える」
私が防災や救助活動について大切だと個人的に感じたことは2つです。
1.助け合い
2.日頃から考えること
老若男女これだけ意識していればもうそれだけでも充分ではないかと思うくらい。
助け合い
防災や救急で最も必要とされるのが助け合いと感じています。
助け合いは誰かがやるもの?組織内だけ?
昨今、自治会などの未加入や高齢化が課題とされていて、それに対して「自治会は防災面で特に必要」と言われるのを目にします。
ということは、自治会に入っていない人のことは「助けない・助けなくていい」と考えているのかといえば、絶対に「はい、そうです」とは言わないと思います。
また、火事の時119に電話しても消防団がない地域は誰も消火活動してくれないのでしょうか。そんなこともない時代です。
自治会に加入していようがしていまいが、日ごろのご近所づきあいは変わらないと思います。
私は自治会理事も経験ありますが、毎年メンバーが同じ。
自治会に加入していても範囲は限られていて、私は所詮、密な関係で日常的に付きあうのは3~4軒先くらいまでなものです。
それに災害時にその自治会区域内に必ずいるという確率は少ないです。
この問題は昔からのシステムがそのまま令和に引き継がれているので、合理的ではない部分がいまの人たちの課題に直面しているのだと思います。
地域・地元への愛着がないこともひとつかもしれませんね。
自治会より自分の所属している団体や会もあるでしょう。
仕事もあります。
土日は休み?
いえいえ、私は長年土日祝日こそ連勤でしたよ。年末年始も職場でした。
江戸時代。
鐘をカンカン鳴らして火事を知らせ、火消し隊が集まり消火。
いまは令和時代。
令和のシステムはどうでしょうか。
けっこう個人の時代になっている感覚です。
先進地域や海外を知ること
日本でも先進的な地域(自治会廃止は武蔵野市が有名)やもしくは海外はどうしているか知ると、一気に視野が広がります。
メディアは一方の主張が強く出されるので、ネガティブ意見が多く打ち出されることも多いですが、一番良いのはそこに住むことです。百聞は一見にしかず。
私が海外にいた時、
「我こそは!」と声をかけ助けたり譲ったりする姿を何度見たことか。
良く言えば正義感か慈悲(宗教観念)、悪く言えばでしゃばりでおしゃべり(笑)。
6車線、信号のない横断歩道近くに歩行者が1人いれば、ほぼ全車が一斉に止まる。
ベビーカー、歩道や階段でほぼ通行人が手助けしてくれる。
飲食店で子どもが泣いてると店員やお客さんが声かけてきてあやしに来る。その間オーダーストップ(笑)。子どもが笑顔になるとお客さん拍手。
アメリカでは救急車やレスキュー車などの緊急車両は、道路で最優先なのですが、本当に爆走でサイレンが超絶うるさいんです。
でも文句言う人もいない。
6車線あっても8車線あっても反対側の車も停まる。
歩いている人たちは手を叩いたりこぶしをあげて声上げて「がんばれよ!たのんだぞ」って応援してる。
全然どこに行くのかもわからない緊急車両に。
緊急車両が帰るときは、子どもも大人も通行人が「よくやったね」と指でピーってしたり、拍手してるんです。
まるでパウパトロールかおさるのジョージの世界じゃないかい。
いつだったか日医大の先生のX Twitterでも同じようなことを言っていて「そうそう!」と懐かしんで見ていました。
気持ちはあっても行動にできない
シャイと言われることが多い我が国民性、
「心の中では助けたいけど何したらよいかわからない。」
スーパーの通路とか電車で横切るとき
「心の中ですみません・・・ありがとう・・・と言ってる。」
そんな感じ。
めちゃくちゃわかります。
アメ人は必ずと言ってよいほど、
知らない人とスーパーの通路ですれ違うだけでも「エクスキューズミー(失礼)」。
見知らぬ人とエレベーター一緒のとき、ほぼほぼ「ハロー、そのバッグいいね!」みたいに話しかけられる。今日も褒めるぜーみたいな国民性。
お店では店員さんが必ず「こんちは。調子はどう?」って。
それが私は結構めんどくさかった。
(英語でどう返事してよいかわからなかった)
スペインはさらに陽気さの味付けをして話しかけてきます。
反対車線の車に手を振って道を聞いてる。後ろの車全ストップ。
そう思うと、帰国して気づいたのは、
思ってることをまっすぐ伝えることよりも、周りの雰囲気に合わせて心で伝えようとするのが日本っぽさ。そういう国民性も好きです。
日本のその雰囲気はもっと自信もって良いと思います。
比較して良いとか悪いとかではなく。これが日本なんだ、って。
その代わり顧客サービス(対お客様)は、たぶん世界一丁寧で細やかな配慮やシステムがなされています。
飛行機の「子どもが座ります座席」表示や「優先席」なんてのも。
このシステムがむしろ、「誰かやってくれる」「困ったら駅員さんや店員さん」という流れになっているのかな。
これを大阪の知人に話したら、「信じられへん!」って言われました。
むしろ「用もあらへんのに声かけるで~」と。
日本でも人によりますし、地域性がありますね。
下町育ちの知人は「昨日〇〇行ってたんだって?」と情報筒抜け。面倒くさいほど人付き合いが盛ん。それ、わかります。
忘れられない私の残念な経験
困ったときはお互い様。
とはいえ普段何気ないときに、「よし救助訓練、防災訓練受けよう!」とはなりませんよね。
ところが、いざ自分の身のまわりで
急に倒れた人がいた、
交通事故に遭遇した、
などのようなことが起こると、何していいかわからない。
私なんか邪魔になるだけだから、心の中で「どうか助かりますように~」と祈りながらその場を見なかったことにしてスルー。
以前、乗降客がすごく多い駅の階段の下で倒れている若い女性がいてピクリとも動かなかったのです。
誰1人声をかけてなかった。
もしくは駅員さんを呼びに行って、すべてを駅員さんに任せていたのかも。
みんな通勤通学で必死だった。
そんなのを乗り換えるためにエスカレーターを上がっていくとき見たことが忘れられなかったです。
そんな私も若すぎて無知すぎて何していいかわからなかった。
これをずっと記憶に残しています。
無謀な正義感は危険?
かといって、事件事故などに遭遇して正義感や助けたい気持ちいっぱいに素手で手助けしたら血液を介して病気が移ってしまった。そんなケースもあるようです。
どんな国・人でも助けあう心がある
でも本当の緊急時は日本であっても海外であっても、みんな恥ずかしがらずに助け合っている姿を私は知っています。
そういう私なんか、学生時代まですっごい内気でしたからね。
今でも私は雰囲気の先入観か、
「パルケさんの前でそんなはしたない話やめなよ。」
とか言って気遣ってもらえますけど、
いやいや東南アジア、アメリカ、ヨーロッパ(アフリカは計画まで)と歩いてきたので、そこでの気づきが今の自分につながっています。
私はたぶん、世界中どこでも住めます。
個人間でみれば、世界の人は優しいって知ってるから。
国は関係なく、人であればどこの国も同じように助け合う社会です。
でも、そこからはみ出させちゃいけません。
区域でメンバーが決められていると、むしろ孤立させてしまったらお互い終わってしまいます。
→ だから自治会が必要、となってしまうのでしょうか。
自治会の意義とか考えずに声をかけることって大事。
なぜならそこにたまたま住んだご縁だから。
これはシステムより教育の問題かと。
でもいざってとき、恥ずかしいですよね・・。
周りに人がいっぱいいても、いなくても、自分から動くってなかなかできませんよね。
そこで次のキーワードになります。
日頃から考える
日常が便利で満たされる環境になればなるほど、いざというとき何していいかわからなくなります。
「自分なんかよりずっと力になる人がいるから。」
「私なんか…。」
「スタッフがやるのが当然でしょ。」
それでも良いと思うんです。
でも、これを読んでいる今、この時に
大きな地震が起きたら?
火山が噴火したら?
火事が起きたら?
家族が倒れたら?
そんな「もしも?」を考える時間を、ふとしたときに考え
こうなったらこうする、を決めておいて
「不安」を小さくしていけば、
目の前の誰か見知らぬ人が倒れていたら自然と体が動くはずです。
少なくとも心は落ち着かせられるはずです。
ここで、1つ目の助け合いに戻ります。
誰でも助けたい気持ちあるけどできない、そんなとき、少しでも知識の付いたあなたが、
「具体的にやってもらう指示を出す」
ことで、助け合いがつながります。
若い女性の心肺停止だったら、
「周りを囲ってください。」
「そこの男性、119番をしてスピーカーにしてください」
「スマホでの撮影をしてる人を注意してください」
「そこの女性、コンビニにAEDがあるので持ってきてください」
など。
この文章から、ちょっとした心のざわつきや反発、興味、意識など、何からのきっかけになってくれたらうれしいです。
記事が長いんじゃ!